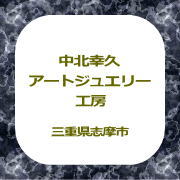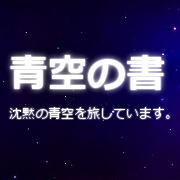中北幸久、伝統の技
「私」の意匠
 先人達が到達し残してくれた技術を引き継ぎ、未来へと繋げていくということなのであるが、ただ習得した技術をそのままに、未来へ繋げていくことが伝統と言えるのであろうか。
先人達が到達し残してくれた技術を引き継ぎ、未来へと繋げていくということなのであるが、ただ習得した技術をそのままに、未来へ繋げていくことが伝統と言えるのであろうか。
先人達も、それ以前からの技術に創意・工夫を加え、新しく発展させてきたのである。そのことを想えば、伝統そのものは大切にしながらも、現在私たちが受け継いで技術もまた、其々が自らの創意・工夫を加え、より優れたものへと進化させていく必要がある。
(これは伝統だから)だからそのままで良いというのは、決してこの好ましいことではない。寧ろそれは伝統というより骨董なのである。
「私」の意匠、として表現されたものが無い限り、その「私」は過去を創造している人ではないだろうか。
根付を現代に…伝統工芸 1
 伝統工芸の一つに根付というものがあるが、現在その多くは、愛好者がそれぞれのケース等に入れて愛玩している場合が常である。その理由に、装いが和服から洋服になり、本来の用途が失われてしまったからである。一部の人は鎖や紐を通してペンダントなどとして使用しているが、この根付という優れた工芸作品は、もっと多くの人が、「私」を表現するものとして使用してもいいのではないだろうか。
伝統工芸の一つに根付というものがあるが、現在その多くは、愛好者がそれぞれのケース等に入れて愛玩している場合が常である。その理由に、装いが和服から洋服になり、本来の用途が失われてしまったからである。一部の人は鎖や紐を通してペンダントなどとして使用しているが、この根付という優れた工芸作品は、もっと多くの人が、「私」を表現するものとして使用してもいいのではないだろうか。
使用しにくい理由として、作品が小振りでありながら高価であるということなのだが、製作する人が少ないというのも現実である。
この小さな根付を、もう少し大きくして海外ブランドの、高級バッグ等の装飾用として展開できないんものだろうか。無論、それに耐えうる高いレベルが求められだろうか。
春慶塗についての私見…伝統工芸 2
 漆が手軽に入手できるようになったためもあってか、最近は漆塗りを楽しむ人が多くなったように思える。その漆塗り工芸の一つに、春慶塗というのがある。素材の木目を生かすために、半透明の透漆(スキウルシ)を使用するのが一般的である。これは金沢や輪島の漆塗りに比べ、せいぜい5・6回塗って仕上げるもので、いわゆる日用雑器の類である。
漆が手軽に入手できるようになったためもあってか、最近は漆塗りを楽しむ人が多くなったように思える。その漆塗り工芸の一つに、春慶塗というのがある。素材の木目を生かすために、半透明の透漆(スキウルシ)を使用するのが一般的である。これは金沢や輪島の漆塗りに比べ、せいぜい5・6回塗って仕上げるもので、いわゆる日用雑器の類である。
基本的には研ぎだしによる表面処理や、蒔絵・沈金等の細工は施さない。作られる物としては、盆・膳・箸・小物入れ等の安価なものが主である。
近年になって製品の種類は増えているものの、その技法は昔のままで、新しい技術による製品はまだ市場にでていない。工芸ではなく、より高い芸術への認識が問われている。
組み紐…伝統工芸 3
 三重県では伊賀の組み紐が有名ではあるが、海外からの安価な製品の進出もあって、産業としては苦境に立たされている。一見手組なのか機械組なのか、素人の私には判断できないものの、近年開発された製品には、携帯電話のストラップやキィーホルダー・ペンダント・ネックレス等、その製品の種類は様々な物がある。しかしながら、その多くは安価な土産物程度の製品であり、産業発展のための打開策には至っていないような気がする。
三重県では伊賀の組み紐が有名ではあるが、海外からの安価な製品の進出もあって、産業としては苦境に立たされている。一見手組なのか機械組なのか、素人の私には判断できないものの、近年開発された製品には、携帯電話のストラップやキィーホルダー・ペンダント・ネックレス等、その製品の種類は様々な物がある。しかしながら、その多くは安価な土産物程度の製品であり、産業発展のための打開策には至っていないような気がする。
大変な作業であると思うが、グラデーションに組み上げ、根付や真珠製品とセットにしていったらどうだろうか。
デザイン…伝統工芸 4
![]() アンモナイトやオオム貝の渦巻き構造、風や波による砂浜の紋様、動植物などの絵柄等々
、自然の中にデザインされたものは無数にある。おそらくこれらのものを見て、人はデザインの着想を得たのであろう。しかし自然界に存在しないであろうと思えるデザインを創造するとなると、至難の業である。況してやそれが立体構造のものとなると、ことさら難しいのである。
アンモナイトやオオム貝の渦巻き構造、風や波による砂浜の紋様、動植物などの絵柄等々
、自然の中にデザインされたものは無数にある。おそらくこれらのものを見て、人はデザインの着想を得たのであろう。しかし自然界に存在しないであろうと思えるデザインを創造するとなると、至難の業である。況してやそれが立体構造のものとなると、ことさら難しいのである。
平面でないものは立体であるというような短絡的な考え方はともかくとして、明確に立体を意識してデザインされたアクセサリーを見かけることは稀である。とりわけ金属による立体構造のアクセサリーとなると、そのものが大きくなればなるほど重量がかさみ、実用的でなくなってしまうという難点がある。しかしアクセサリーだからということで、あまりにも素材の(金・銀・プラチナ)に拘り過ぎているのではないだろうか。
開かれていない扉を開いていく努力が必要な時代ではないだろうか。